- 「副業で簡単に高収入を得られる」などと偽り、金銭を支払わせようとする詐欺
- 登録料、マニュアル代、サポート費用、システム利用料などの名目で金銭を騙し取る
- 実際には約束された収入は得られず、金銭的損失や個人情報流出、さらなる詐欺被害の可能性

もっとくわしく知りたい方は続きをどうぞ!
副業詐欺をわかりやすく
副業詐欺とは
副業詐欺の主な目的は、副業を探している人々の「手軽に収入を増やしたい」という願望や経済的な不安につけ込み、様々な口実で金銭を騙し取ることにある。基本的な概念としては、まず「誰でも簡単に」「スマホだけで」「短時間で高収入」といった魅力的な言葉でターゲットを誘い込む。これは、多くの人が持つ楽して稼ぎたいという心理を巧みに利用する手口。
一度興味を持ったターゲットに対し、具体的な仕事内容を曖昧にしたまま、登録料や教材費、高額なサポート契約、システム利用料といった名目で金銭の支払いを要求する流れが一般的。詐欺師は、あたかもその支払いが副業で成功するために必要不可欠であるかのように説明する。しかし、実際には約束されたような収入を得ることはできず、支払ったお金は戻ってこないケースがほとんど。簡単な作業で高収入が得られるかのような誤解を与え、金銭を詐取することが、この詐欺の核心部分と言える。
副業詐欺の具体的な例
副業詐欺は、様々な形で私たちの身近に潜んでいる。以下に、具体的な手口の例をいくつか挙げる。
- 情報商材詐欺:SNSの広告や検索サイトで見つけた「ネットで簡単に稼ぐ方法」という情報に惹かれ、数千円から数十万円する情報商材(PDFや動画教材)を購入するケース。しかし、内容はインターネットで無料で手に入るような情報だったり、具体性がなく役に立たなかったりすることが多い。さらに、「より稼ぐためには高額なサポート契約が必要」などと、追加の支払いを要求されることもある。
- タスク詐欺(作業報酬型詐欺):TikTokやInstagramなどのSNS広告で「動画を見るだけ」「いいねを押すだけ」「スクリーンショットを送るだけ」といった簡単な作業で報酬がもらえると勧誘される。最初は数百円程度の少額報酬が実際に支払われるため、信用しやすい。しかし、その後「より高額な報酬を得るためのタスク」に参加するために、数万円から数十万円の参加費や保証金の支払いを要求される。作業ミスを理由に追加支払いを求められたり、最終的に報酬は支払われず、支払ったお金も戻ってこなかったりする。
- 投資勧誘型詐欺:副業の紹介と見せかけて、「必ず儲かる」「元本保証」などと謳い、FXや暗号資産(仮想通貨)、未公開株などへの投資を勧誘する手口。専用サイトへの登録料や、高額な自動売買ツールの購入を勧められることもある。SNSで知り合った相手から恋愛感情を利用して投資に誘われるロマンス詐欺の要素を含む場合もある。実際には運用されず、出金しようとすると様々な理由をつけて拒否されたり、連絡が取れなくなったりする。
- 内職・あっせん・資格詐欺:「在宅ワークで高収入」「稼げる副業を紹介する」などと言って登録料や会員費を支払わせたり、「仕事を始めるために必要」として高額な機材や商品を購入させたりするが、実際には仕事を紹介しない手口。また、「資格を取得すれば仕事を紹介する」として高額な教材を売りつけるが、サポートがなかったり、資格自体が役に立たなかったりするケースもある。
- 出会い系サイト・サクラ詐欺:主に女性をターゲットに、「男性からのメールに返信するだけで高収入」「悩み相談に答えるだけで稼げる」などと誘い、出会い系サイトやアプリに登録させる。実際には、サイト利用料やポイント購入費用、報酬受け取りのための手数料などの名目で金銭を要求される。相談相手は運営側が用意したサクラである場合が多い。
これらの手口は単独で行われるだけでなく、組み合わされることも多い。例えば、情報商材を購入させた後に高額なコンサルティング契約を勧めたり、タスク詐欺から投資詐欺に誘導したりする。詐欺師は常に新しい手口を開発しており、その多様性を認識することが重要。
副業詐欺が発生する手順
- 1勧誘・接触
インターネット広告(Google検索結果、YouTube広告など)、SNS(Instagram、X、TikTok、Facebookなど)の投稿や広告、ダイレクトメッセージ(DM)などを通じて、「簡単に稼げる」「高収入」「スマホだけでOK」といった魅力的な言葉でターゲットに接触する。副業紹介サイトやランキングサイトを装うこともある。
- 2個別連絡への誘導
興味を示したターゲットを、LINEやTelegram、その他のメッセージアプリといった、1対1でのやり取りが可能な閉鎖的なコミュニケーションツールへ誘導する。これにより、外部からの監視を避け、ターゲットを個別に説得しやすくなる。詐欺発覚後にアカウントをブロックして連絡を絶つことも容易になる。
- 3信用獲得(信頼醸成)
すぐに金銭を要求するのではなく、まず簡単な作業(動画視聴、スクショ送信、いいね、アンケート回答など)を指示し、それに対して数百円程度の少額報酬を実際に支払う。これにより、「本当に稼げる」「この話は信用できる」とターゲットに思い込ませ、心理的な警戒心を解く。これは、後の高額請求を受け入れさせるための巧妙な罠。
- 4本題への移行・情報提供
ターゲットが信用した段階で、本題である「より高収入を得るための方法」として、情報商材の購入、有料サポートプランへの加入、投資案件への参加などを持ちかける。電話やオンライン会議ツール(Zoomなど)で直接説明し、断りにくい状況を作ることもある。
- 5支払い要求とエスカレーション
マニュアル代、登録料、システム利用料、サポート費用、保証金などの名目で、数万円から時には百万円を超える高額な支払いを要求する。支払いを渋ると、「今だけ割引」「限定枠」などと決断を急がせたり、「すぐに元が取れる」「これで確実に稼げる」と説得したりする。お金がないと断ると、消費者金融からの借金を勧め、遠隔操作アプリを使って手続きを手伝う悪質なケースもある。一度支払うと、さらに高額なプランや追加費用を次々と要求されることが多い。
- 6問題発生と連絡途絶
ターゲットが高額な支払いをした後、約束された収入は得られず、サポートも実質的に行われないことが多い。返金を求めたり、苦情を言ったりすると、相手は連絡を無視したり、アカウントをブロックしたりして姿を消す。タスク詐欺では、「作業ミスで損失が出た」などとターゲットに責任転嫁し、さらなる支払いを要求することもある。
- 7被害発覚・相談
ターゲットは多額の金銭を失い、借金だけが残ることもある。ここで初めて詐欺だと気づき、消費生活センターや警察、弁護士などに相談するケースが多い。
副業詐欺による事件
副業詐欺に関連する事件は後を絶たないが、特に社会的な注目を集め、その深刻さを示す事例として、2020年に起きた投資マルチ商法による22歳女性の自殺事件がある。
この事件では、新社会人となったばかりのKさんが、大学時代の同級生からSNSを通じて「投資に興味があるか」と声をかけられたことが発端となった。当初は軽い気持ちで応じたが、同級生と、その紹介者である投資グループの勧誘担当者から執拗な勧誘を受けた。LINEでのやり取りは100件以上に及び、「マルチとかネズミ(講)ではない」「何もしなくてもお金は入ってくる」「紹介すればさらに利益が出る」といった言葉で、不労所得への期待感を煽られた。
Kさんは350万円ほどの奨学金返済を抱えており、経済的な不安もあったことから、同級生らに押し切られる形で消費者金融3社から合計150万円を借り入れ、全額を勧誘担当者に渡してしまった。しかし、約束された配当金が支払われることはなかった。
返金を求めて同級生らのもとを訪れた際も、彼らは「会社がやっていることで、自分たちは関係ない」と責任を回避し、真摯な対応は見られなかった。精神的に追い詰められたKさんは、うつ状態と診断され、最終的に自ら命を絶つという悲劇的な結末を迎えた。遺書には、母親への感謝と共に、投資詐欺で迷惑をかけたことへの謝罪が記されていた。
この事件で使用された「ジェンコ」や「ジュビリーエース」といった金融商品は、高配当を謳い文句にマルチ商法的に出資者を増やしていく典型的なポンジ・スキーム(自転車操業的な詐欺)の疑いが強いものであった。事件後、投資グループのリーダー格や勧誘担当者は金融商品取引法違反で逮捕・起訴されたが、リーダーは執行猶予付き判決、勧誘担当者は罰金刑にとどまり、Kさんを直接勧誘した同級生は罪に問われなかった。
この事件は、友人関係という信頼関係が悪用されること、若者が経済的な不安や知識不足からターゲットにされやすいこと、そして詐欺被害が金銭的損失だけでなく、人の命をも奪いかねない深刻な精神的苦痛を与えることを浮き彫りにした。また、法的な処罰が被害の実態に見合っていないのではないか、詐欺罪としての立件はできなかったのか、といった問題点も指摘されている。同様の投資マルチ詐欺や、SNSを悪用した副業詐欺は依然として多く発生しており、この事件は決して他人事ではない教訓を残している。
副業詐欺についてのよくある質問
- Q「誰でも簡単に」「すぐに高収入」といった広告は信用できるのか?
- A
信用するな。「誰でも」「簡単に」「すぐに」「確実に」といった言葉で高収入を謳う広告は、副業詐欺の典型的な誘い文句。現実的に、特別なスキルや努力なしに高収入を得られる仕事はほとんど存在しないと考えた方が安全。また、「絶対」「必ず」といった断定的な表現は、景品表示法で禁じられている誇大広告にあたる可能性があり、まともな企業であれば通常使用しない。
- Q仕事を始める前に、登録料や教材費などの初期費用を要求された。支払うべきか?
- A
支払うべきではない。仕事を始める前にお金を要求するのは、副業詐欺の非常に一般的な手口。正規の雇用や業務委託では、働く側が事前にお金を支払うケースは稀。マニュアル代、システム利用料、研修費、保証金など、様々な名目が考えられるが、安易に支払わないことが重要。途中で支払いを求められた場合も、すぐに手を引くべき。
- Q「稼げるノウハウ」を教えるという情報商材は本当に役立つのか?
- A
役立たない、あるいは価格に見合わない価値のないものが大半。インターネットで検索すれば分かるような一般的な情報しか書かれていなかったり、内容が古かったり、具体的でなかったりするケースが多い。購入してみないと中身が分からないという情報商材の特性が悪用されている。さらに、情報商材購入後に高額なサポート契約やコンサルティング契約に誘導される二次的な被害も多い。
副業詐欺が生まれた歴史や背景
副業詐欺が近年特に増加し、注目されるようになった背景には、いくつかの社会的要因が複合的に絡み合っている。
- 働き方の変化と副業解禁:働き方改革の推進により、副業を解禁または推奨する企業が増加した。これにより、副業への関心が高まり、副業を探す人が増えたことが、詐欺師にとってのターゲット層拡大につながった。
- 経済的不安と収入増への希求:長引く経済の低迷や将来への不安感から、本業以外での収入源を求める人が増えている。特に若年層においては、給与水準への不満や、SNSなどで目にする華やかな生活への憧れから、「手軽に稼ぎたい」という心理が働きやすい。国が投資を推奨する動きも、知識のないまま安易に儲け話に乗ってしまう土壌を作っている側面がある。
- インターネットとスマートフォンの普及:インターネットやスマートフォンの普及により、誰もが簡単に情報にアクセスし、オンラインで完結する仕事を探せるようになった。これはlegitimateな副業機会を増やす一方で、詐欺師にとっても匿名性を保ちながら不特定多数にアプローチすることを容易にした。
- SNSの浸透:Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、LINEなどのSNSは、情報拡散力が高く、個人間のコミュニケーションも容易であるため、詐欺の温床となりやすい。魅力的な生活を見せつけて信用させたり、DMで直接勧誘したり、広告を大量に表示したりと、多様な手口で利用されている。
手口の進化
副業詐欺の手口は、時代と共に巧妙化・多様化してきた。
- 古典的な手口:かつては、内職商法(簡単な手作業を斡旋すると言って材料費や登録料を騙し取る)や、資格商法(資格取得を支援すると言って高額な教材を売りつける)などが主流であった。
- 情報商材の登場:インターネットの普及に伴い、「稼げるノウハウ」を謳った情報商材を販売する手口が登場し、一時期急増した。
- スマホ副業詐欺の隆盛:スマートフォンだけで完結するように見せかける手口が増加。特にSNSを悪用した勧誘が主流となっている。
- タスク詐欺の出現:近年、「いいねを押すだけ」「動画を見るだけ」といった簡単なタスク(作業)で報酬を支払うと見せかけ、最終的に高額な金銭を要求する「タスク詐欺」が急増している。
- 技術の悪用:暗号資産(仮想通貨)や遠隔操作アプリなど、新しい技術を悪用した手口も次々と現れている。これは、詐欺師が常に最新の技術動向に適応し、法規制や対策の隙を突こうとしていることを示唆する。
社会的影響
副業詐欺は、単なる金銭被害にとどまらず、深刻な社会問題となっている。被害額は依然として高水準であり、特に社会経験の浅い若年層がターゲットにされやすい傾向がある。さらに悪質なケースでは、被害者が知らず知らずのうちに詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪行為に加担させられる「闇バイト」のような事例も報告されている。こうした状況を受け、消費者庁や国民生活センター、警察などが連携し、継続的に注意喚起や対策強化を行っている
副業詐欺の被害にあってしまいやすい人物や状況
副業詐欺の被害に遭わないためには、どのような人が狙われやすく、どのような状況で騙されやすいのか、そしてどのような落とし穴があるのかを知っておくことが重要。
被害に遭いやすい人物像
- 収入増を切望する人:現在の収入に不満がある、借金がある、将来のためにお金を貯めたいなど、切実にお金を必要としている人は、「簡単に稼げる」という誘惑に弱くなりやすい。
- 若年層・社会経験の浅い人:社会経験が少ないため、うまい話の裏を見抜くのが難しかったり、契約に関する知識が不足していたりすることがある。また、SNSの利用時間が長く、オンラインでの情報収集やコミュニケーションに慣れている反面、情報の真偽を見極める力が未熟な場合もある。成人年齢引き下げにより、未成年者取消権が使えなくなる18歳、19歳が特に狙われやすくなっている点も注意が必要。
- 「自分は大丈夫」という過信がある人:「自分は騙されない」と思い込んでいる人は、かえって警戒心が薄れ、詐欺師の巧妙な話術に乗せられてしまう危険性がある。
- 心理的な弱さを持つ人:自分の欲求をコントロールするのが苦手な人、人を信じやすい人、権威や論理的な説得に弱い人は、詐欺師のターゲットにされやすい傾向が指摘されている。
- 孤立している人:周囲に相談できる相手がいない、あるいは相談しにくい状況にある人は、一人で問題を抱え込み、詐欺師の言いなりになってしまうことがある。
被害に遭いやすい状況
- SNSやネット広告での接触:日常的に利用するSNSやインターネット上で、「副業」「簡単」「高収入」などのキーワードで検索したり、魅力的な広告を目にしたりしたときが、詐欺への入り口となることが多い。
- 知人からの勧誘:友人、先輩、同僚など、信頼している人物から儲け話を持ちかけられた場合、疑う気持ちが薄れ、話に乗ってしまいやすい。特にマルチ商法では、人間関係を利用した勧誘が常套手段。
- 決断を急かされる状況:「今だけ限定」「キャンペーン期間中」「残り○名」などと言われ、冷静に考える時間を与えられずに契約を迫られたとき。焦りや「機会を逃したくない」という心理が働き、不利な契約を結んでしまうことがある。
- 高額な支払いを求められた時:初期費用やサポート料として高額な支払いを求められ、断ると「これまでの投資が無駄になる」「違約金が発生する」などと脅されたり、「必ず元は取れる」と説得されたりして、断りきれなくなる状況。
副業詐欺の見分け方
以下の項目に一つでも当てはまる場合は、副業詐欺の可能性が高いと考え、警戒する必要がある。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 条件が良すぎる | 「誰でも」「簡単に」「スキル不要」「短時間で高収入」「スマホだけで月収〇〇万円」など、現実離れした好条件を提示している。 |
| 極端・断定的な表現 | 「絶対」「必ず」「100%儲かる」「確実に稼げる」「元本保証」などの言葉を使っている。成功体験談ばかりを強調している。 |
| 事前支払いの要求 | 仕事を始める前に「登録料」「教材費」「マニュアル代」「システム利用料」「保証金」「サポート費用」などの名目で支払いを要求する。 |
| 仕事内容が不明確 | 具体的な業務内容、作業時間、報酬の仕組み、収益モデルなどの説明が曖昧で、質問してもはっきり答えない。 |
| 運営者情報が不審 | 運営会社の名称、所在地、電話番号などの情報が記載されていない、または検索しても実在が確認できない。特定商取引法に基づく表示がないか不十分。 |
| SNSでの勧誘 | 見知らぬアカウントからのDMや、急に親しげに近づいてくるメッセージ。過度に裕福な生活(高級車、ブランド品、旅行など)を見せつけるアカウントからの勧誘。 |
| 個人名義口座への振込指示 | 費用や投資金の振込先として、個人名義の銀行口座を指定される。 |
| 借金の推奨 | 費用が支払えないと伝えると、安易に消費者金融からの借金を勧められる。手続きを代行しようとしたり、遠隔操作アプリを求めてきたりする。 |
| 連絡手段の限定 | LINEやTelegramなど、特定のメッセージアプリのみでのやり取りを強要し、電話番号を教えない、または電話に出ない。 |
| 急かす・焦らせる言動 | 「今だけ」「限定」「早くしないと損」などと、考える時間を与えずに契約や支払いを急かせる。 |
副業詐欺のまとめ
- 副業詐欺は、「簡単」「高収入」といった甘い言葉で誘い込み、登録料、教材費、サポート料などの名目で金銭を騙し取る悪質な犯罪で、情報商材、タスク詐欺、投資勧誘型など手口は多様化・巧妙化しており、常に注意が必要
- 「条件が良すぎる」「事前にお金を要求する」「運営者情報が不明」「SNSで勧誘してくる」「個人名義口座へ振込を指示する」といった点は、副業詐欺を見抜くための重要なチェックポイントとなので、これらの特徴に一つでも当てはまれば、詐欺を強く疑うべき
- 被害を防ぐためには、安易に情報を信じず、契約前に運営元や契約内容を十分に確認し、少しでも怪しいと感じたら絶対に契約・支払いをせず、速やかに消費生活センター、弁護士などに相談

以上、副業詐欺についてでした!これで、副業詐欺はあなたの知識となりましたか?
被害にあわないように対策しましょう。まだまだ足りないという方は、コメントをぜひください。お待ちしております。

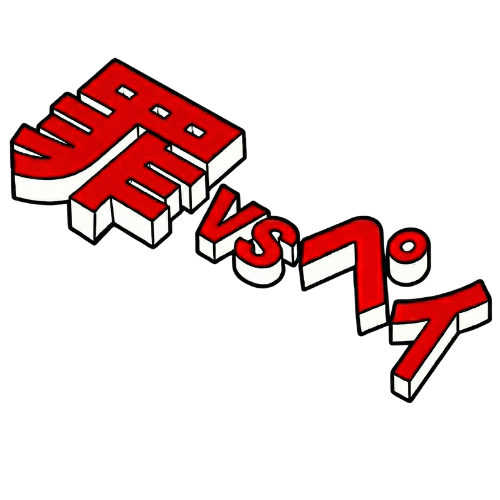


コメント