- 起訴された被告人が一時的に身柄を解放されるために裁判所に納めるお金
- 被告人の逃亡や証拠隠滅を防ぎ、裁判への出頭を保証するのが目的
- 原則は、裁判終了後、保釈条件を守れば全額返還される

もっとくわしく知りたい方は続きをどうぞ!
保釈金の目的と基本的な概念
保釈金とは
保釈金(正式には保釈保証金ともいう)は、起訴された被告人が、判決が確定するまでの間、逃亡や証拠隠滅を防ぐための担保として、裁判所に納める金銭のことである。これは、被告人が裁判期日にきちんと出頭することを保証する目的も持つ。保釈制度は、推定無罪の原則に基づき、必要以上に被告人の身柄拘束を続けるべきではないという考え方から存在する。起訴されたとはいえ、有罪判決が確定するまでは無罪の人と同様に扱われるべき。
日本の刑事裁判においては、起訴される前段階である逮捕・勾留の期間が比較的長く、国際的に見ても異例であるという指摘がある。このような状況を踏まえ、起訴された被告人に対しては、一定の条件のもとで身柄を解放する制度が設けられている。それが保釈。身体拘束されたままでは、裁判のための準備をするにも制約を受けるため、保釈は被告人の権利を保障する上でも重要な意味を持つ。
ただし、保釈は無条件に認められるわけではない。逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどが条件となる。裁判所は、被告人の性格、犯罪の種類、証拠の状況などを総合的に考慮して、保釈を許可するかどうかを判断する。保釈金は、もし被告人が逃亡したり、裁判所の定めた条件に違反した場合に没収される可能性がある。このような経済的な負担を課すことで、被告人に保釈中に定められたルールを守らせるという抑止力として機能する。保釈金は、単なる身代金ではなく、被告人の行動を律するための保証としての意味合いが強いと言える。
保釈金の具体的な例
日常的な例え
例えば、賃貸契約における敷金(保証金)に似ている。敷金は、家賃滞納や物件の破損がなければ、契約終了後に返還される。保釈金も同様に、裁判手続きが問題なく終了すれば返還される。ただし、家賃を滞納したり、部屋をひどく汚したりすると敷金が返還されないように、保釈金も条件違反があれば没収される。この例えは、保釈金が一時的に預けるお金であり、問題がなければ戻ってくるという基本的な仕組みを理解するのに役立つ。
具体的な例
- 被告人が窃盗罪で起訴され、保釈金200万円を納付して釈放された。裁判には毎回出廷し、証拠隠滅などの行為もなかったため、裁判終了後に200万円は全額返還された。このケースは、一般的な犯罪における保釈の流れを示しており、保釈金が被告人の出頭を促し、条件を満たせば返還されることを明確に示している。
- 著名な経済事件で、被告人が海外逃亡のおそれがあると判断され、5億円の保釈金が設定された。これは、被告人の資産状況や事件の重大性を考慮した結果。高額な保釈金は、被告人にとって没収された場合の経済的な打撃が大きいため、逃亡を思いとどまらせる効果が期待される。
- 保釈中に被告人が被害者に接触する行為が確認され、保釈が取り消され、納付していた保釈金の一部が没収された。この事例は、保釈には様々な条件が付随しており、それらの条件を遵守しなければ保釈が取り消され、保釈金が没収される可能性があることを示している。保釈の条件は、事件の内容や被告人の状況によって個別に定められる
保釈金が発生する手順を順番に解説
- 1起訴
検察官が証拠に基づいて、被告人を刑事裁判にかけることを決定する。これは、捜査の結果、犯罪の嫌疑が濃厚であると判断された場合に行われる。起訴状が裁判所に提出されることで、正式な刑事裁判の手続きが開始される。
- 2保釈請求
起訴後、被告人または弁護人が裁判所に対して保釈を求める。これは通常、保釈請求書という書面を提出して行われる。保釈請求書には、保釈を求める理由や、被告人が逃亡や証拠隠滅をしないことを示す具体的な内容を記載する必要がある。本人や家族も保釈請求は可能だが、実際には弁護人が行うのが一般的。
- 3裁判官の審査・検察官の意見
裁判官は、保釈を認めるかどうかを判断するために、事件の内容、被告人の状況、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを審査する。また、検察官の意見も聴取される。裁判官は、保釈請求書の内容や提出された証拠、検察官の意見などを総合的に考慮し、保釈の可否を判断する。場合によっては、裁判官が被告人と面談することもある。
- 4保釈許可決定
裁判官が保釈を認める決定を下す場合、保釈金の金額や保釈中の条件(住居制限、旅行制限など)が決定される。保釈許可決定には、保釈金の金額だけでなく、被告人が守るべき様々な条件が記載される。これらの条件は、被告人の逃亡や証拠隠滅を防ぐために設定される。
- 5保釈金の納付
決定された保釈金を、被告人またはその家族が裁判所に納付する。原則として現金での納付となるが、最近は電子納付も可能になっている場合がある。保釈金は、裁判所の出納課に納付される。弁護士が家族から預かった保釈金を裁判所に納付することも多い。
- 6被告人の釈放
保釈金の納付が確認されると、裁判所から検察庁、そして留置施設へと連絡が行き、被告人が釈放される。保釈金の納付手続きが完了すると、通常、数時間以内に被告人は釈放される。ただし、裁判所や検察庁の事務手続きの状況によっては、時間がかかる場合もある。
- 7裁判手続きの進行
保釈された被告人は、保釈中に定められた条件を守りながら、刑事裁判に出席する。保釈期間中も、被告人は引き続き裁判手続きに参加し、自身の事件について審理を受ける必要がある。保釈条件に違反すると、保釈が取り消される可能性がある。
- 8裁判終結と保釈金の返還
裁判が終了し、被告人が逃亡や条件違反などをしていなければ、納付された保釈金は全額返還される。返還時期は、判決確定後、通常数日から1週間程度である 。保釈金は、原則として被告人が納付した際の口座に振り込まれる。
保釈金に関して有名な事件
- ハンナン牛肉偽装事件: 食肉偽装事件で逮捕された被告に対し、過去最高額となる20億円の保釈金が設定された。これは、被告人の資産状況や社会的影響力を考慮した結果とされる。巨額の保釈金は、被告人の逃亡を阻止するための強い抑止力となると考えられた。この事件は、保釈金の金額が被告の経済力によって大きく左右されることを示す好例。一般的に保釈金の相場は150万円から300万円程度であることを考えると、20億円という金額は極めて異例。
- カルロス・ゴーン事件: 日産自動車の元会長であるカルロス・ゴーン被告は、複数の罪で起訴され、総額15億円の保釈金を納付して保釈された後、日本から国外へ逃亡した。この事件は、高額な保釈金が必ずしも逃亡を防ぐとは限らないこと、また、保釈中の被告人に対する監視体制の課題を浮き彫りにした。ゴーン被告は、保釈中に裁判所の許可を得ずに国外に渡航し、日本の司法制度に大きな衝撃を与えた。この事件は、保釈制度の限界を示す事例として、国内外で大きな議論を呼ん。保釈金制度は、被告人の出頭を保証するためのものだが、被告人の強い意志があれば、それを完全に防ぐことは難しいという現実を示唆している。
保釈金についてのよくある質問
- Q保釈金の相場はいくらくらいですか?
- A
一般的には150万円から300万円程度であることが多いです。しかし、被告人の収入や資産、犯罪の種類や情状などによって大きく変動します。高収入の被告や重大な犯罪の場合には、数千万円から数億円になることもあります。例えば、有名人や資産家の場合には、高額な保釈金が設定される傾向があります。罪名別の保釈金の相場としては、窃盗で150万円~200万円、傷害で150万円~200万円、不同意わいせつで200万円~250万円、不同意性交等で300万円前後などが目安とされています。
- Q保釈金は必ず返ってくるのですか?
- A
原則として、裁判所の定めた保釈条件を守り、裁判に出席すれば全額返還されます。しかし、逃亡したり、証拠隠滅を図ったり、被害者等に接触したりするなど、保釈条件に違反した場合は、全部または一部が没収されることがあります。保釈金は、保釈制度の利用料金ではなく、あくまで逃亡を抑止するための保証金という性質を持ちます。
- Q保釈金が用意できない場合はどうすればいいですか?
- A
保釈金が用意できない場合でも、日本保釈支援協会などの保証金立替制度を利用できる可能性があります。このような団体は、一定の審査や手数料が必要となりますが、保釈金の立て替えを支援してくれます。また、弁護士が保釈保証書を発行する制度を利用できる場合もあります。これは、現金での納付の代わりに、保証書を裁判所に提出することで保釈が認められる制度です。
- Q保釈の手続きはどのように進めればいいですか?
- A
保釈を希望する場合は、まず弁護士に相談するのが一般的です。弁護士は、保釈請求の手続きを代行したり、裁判所との交渉を行ったりしてくれます。保釈請求は、裁判所に保釈請求書を提出して行います。保釈請求書には、保釈を認めるべき理由を具体的に記載する必要があります。
- Q保釈金はいつ返還されますか?
- A
保釈金は、裁判がすべて終了し、判決が確定した後、通常数日から1週間程度で返還されます。無罪判決や執行猶予判決の場合は比較的早く、実刑判決の場合は被告人が刑務所に収容された後に返還されることが多いです。返還方法は、事前に指定した銀行口座への振り込みが一般的です。保釈金を納付する際に、返還先の口座情報を裁判所に提出します。
保釈金の相場
| 罪名 | 保釈金の相場 (目安) |
|---|---|
| 窃盗 | 150万円~200万円 |
| 傷害 | 150万円~200万円 |
| 不同意わいせつ | 200万円~250万円 |
| 不同意性交等 | 300万円前後 |
| 大麻 | 200万円前後 |
| 詐欺 | 250万円前後 |
| 強制性交等 | 300万円前後 |
| 横領・背任 | 被害額による差が大きい |
| 殺人 | 保釈が認められる可能性は低い |
保釈金が生まれた歴史や背景
保釈制度の起源は古く、人質制度に遡るとも言われている。中世ヨーロッパでは、犯罪者を拘束する代わりに、信頼できる第三者を人質として差し出すことで、逃亡を防ぐ仕組みが存在した。これは、現代の保釈制度における身元保証人の考え方に繋がるものと考えられる。
近代的な保釈制度は、被告人の権利保護の観点から発展してきた。逮捕・勾留による身体拘束は、被告人にとって大きな負担となるため、起訴後は一定の条件のもとで身柄を解放し、社会生活を送りながら裁判の準備ができるようにする目的がある。罪を犯した疑いのある人であっても、裁判で有罪が確定するまでは無罪として扱われるべきであるという「推定無罪の原則」の考え方が、保釈制度の根底にある。
日本においては、明治時代に制定された刑事訴訟法において、近代的な保釈制度が導入された。これは、欧米の法制度を参考にしながら、日本の社会状況に合わせて整備されたもの。その後、時代の変化や社会情勢に合わせて、制度の見直しや改正が行われてきた。例えば、保釈金の金額の決定基準や、保釈条件の内容などが、社会の変化に合わせて調整されてきた。
保釈金のまとめ
- 保釈金は、起訴された被告人が一時的に身柄を解放されるために裁判所に納める保証金であり、逃亡や証拠隠滅を防ぎ、裁判への出頭を保証する目的がある
- 保釈金の相場は事案によって大きく異なるが、一般的には150万円から300万円程度。裁判終了後、保釈条件を守れば原則として全額返還される
- 保釈を希望する場合は、弁護士に相談し、保釈金が用意できない場合は保釈支援制度の利用も検討できる。保釈中は裁判所の定めた条件を遵守することが重要である

以上、保釈金についてでした!これで、保釈金はあなたの知識となりましたか?
被害にあわないように対策しましょう。まだまだ足りないという方は、コメントをぜひください。お待ちしております。

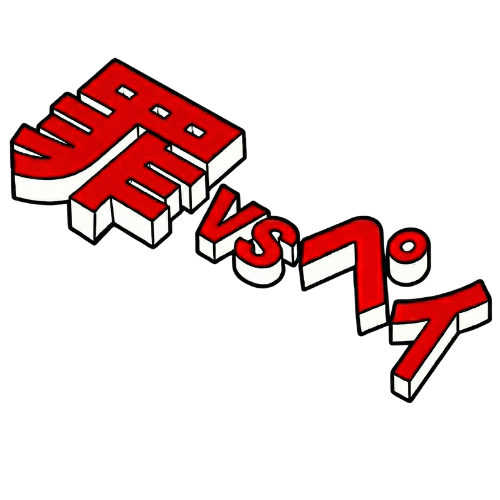


コメント