- 投資家から集めた資金を運用せず、後から参加した人の出資金を先に参加した人へ配当として渡す自転車操業の詐欺のことだ。
- 実際に利益が出ているように装うことで信用を勝ち取り、さらに巨額の資金を投じさせてから首謀者が資金を持って逃走する仕組みだろう。
- 配当が支払われている間に資金を引き揚げようとしても、様々な理由をつけて拒否され、最終的に全額を失うわけがないと過信してはならない。

この4コマ漫画で描かれている事例は、投資詐欺の古典的かつ典型的な手法であるポンジスキームの縮図です。被害者は「年利30%超」「元本保証」という、通常の金融市場ではあり得ない好条件を提示され、冷静な判断力を失ってしまいます。
なぜ多くの人が騙されてしまうのでしょうか。それは、漫画の2コマ目のように、初期段階では実際に配当金が支払われるためです。しかし、これは運用益ではなく後から参加した出資者の元本を配当に回しているだけの自転車操業に過ぎません。被害者は自分がお金を増やしていると錯覚し、周囲の人々まで勧誘してしまうことで被害が拡大します。
最終的には新たな出資者が途絶えた時点でシステムは破綻し、運営者は資金を持ち逃げします。法的に見ても、元本保証を謳って不特定多数から資金を集める行為は出資法違反となる可能性が極めて高いです。「絶対に儲かる」「元本保証」という言葉が出たら詐欺と疑い、決して手を出さないことが最大の防御策となります。
【深掘り】これだけは知っておけ
この手口が100年以上も横行し続けている理由は、初期段階では約束通りに配当金が支払われる点にあります。参加者は通帳に振り込まれる数字を見て投資が成功していると誤認し、知人を紹介したり追加融資を受けたりして被害を拡大させてしまいます。しかし、実態としての事業収益は存在しないため、新規の出資者が減った瞬間にシステムは即座に崩壊するのです。
典型的なフレーズ・文脈

独自のAIアルゴリズムで運用しており、元本保証で毎月5パーセントの配当を約束します。
詐欺師が投資家を勧誘する際の定番フレーズです。最新技術や元本保証という言葉で安心感を与え、冷静な判断を奪います。

被告人は虚偽の投資話を持ちかけ、全国の高齢者らから計100億円を不正に集めた疑いがある。
ニュース報道において、事業の実態がないまま資金を集めた組織的詐欺の構図を説明する際に使われます。

現在、システムの不具合で出金制限がかかっていますが、来月には解消される見込みです。
資金繰りが行き詰まった際、首謀者が逃走準備をするための時間稼ぎとして投資家へ送るメッセージの典型です。
【まとめ】3つのポイント
- 底の抜けた貯金箱:預けたお金は運用されることなく、そのまま別の参加者の財布や首謀者の隠し口座へと消えていく。
- 特別感の悪用:自分だけが選ばれたという特権意識を植え付け、疑う心を麻痺させることで被害者を加担者へと変貌させる。
- 公的登録の確認:金融庁のサイトで免許・許可・登録を受けている業者名簿を確認し、記載がない場合は即座に交渉を打ち切る。
よくある質問
- Qポンジスキームとネズミ講との違いは何ですか?
- Aネズミ講は主に商品の販売組織を装い、紹介料で利益を得る構造ですが、ポンジスキームは投資運用を装い、配当金として資金を分配するふりをする点が異なります。
- Q最初の数ヶ月は配当が振り込まれているので、本物の投資ではないですか?
- Aいいえ、それこそが撒き餌です。信用させてさらに多額の資金を投じさせ、知人を勧誘させるためのコストとして、あなたの元本の一部が返ってきているだけに過ぎません。
- Q紹介料をもらって知人を誘ってしまった場合、私も罪に問われますか?
- A実態を知らなくても、無登録で勧誘行為を行った場合は金融商品取引法違反に問われるリスクがあります。また、知人から損害賠償を請求される可能性も非常に高いです。
- Q海外に拠点がある投資会社だと言われましたが、安心でしょうか?
- Aむしろ危険です。日本の法律が届きにくい場所を拠点に選ぶのは、トラブル時に法的追及から逃れるための計算された戦略であることがほとんどです。
ポンジスキームが生まれた歴史や背景

チャールズ・ポンジ(Charles Ponzi, 1882年3月3日 – 1949年1月18日) 出典:Boston Library (NYT); en.wikipedia.org – Boston Library (NYT); en.wikipedia.org, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31534797による
ポンジスキームという名前は、20世紀初頭にアメリカで詐欺事件を起こしたチャールズ・ポンジという人物に由来する。ポンジは1919年、国際返信切手券を使った投機ビジネスを始め、「90日間で40%の利回り」という高配当を謳って投資家から資金を集めた。彼は、国際返信切手券の価格差を利用すれば利益が出ると嘘の説明をしていた。
しかし実際には、切手券への投資はほとんど行わず、後からの出資者の資金を以前の出資者への配当に充てていた。彼は投資を一切行っていなかった。彼の詐欺は1920年に新聞報道によって明るみに出て破綻し、多くの被害者を出した。金融誌が彼のビジネスモデルの矛盾点を指摘したことがきっかけだった。
興味深いことに、ポンジ以前にも同様の手法を使った詐欺は存在していたと言われている。19世紀にはすでに報告があり、チャールズ・ディケンズの小説にもその手法が描かれている。そして近年では、仮想通貨やインターネット技術を悪用した新たな形のポンジスキームも登場している。例えば、「必ず儲かる」「年利10%以上は間違いない」などと甘い言葉で誘い、暗号資産への投資を勧める詐欺が増えている。


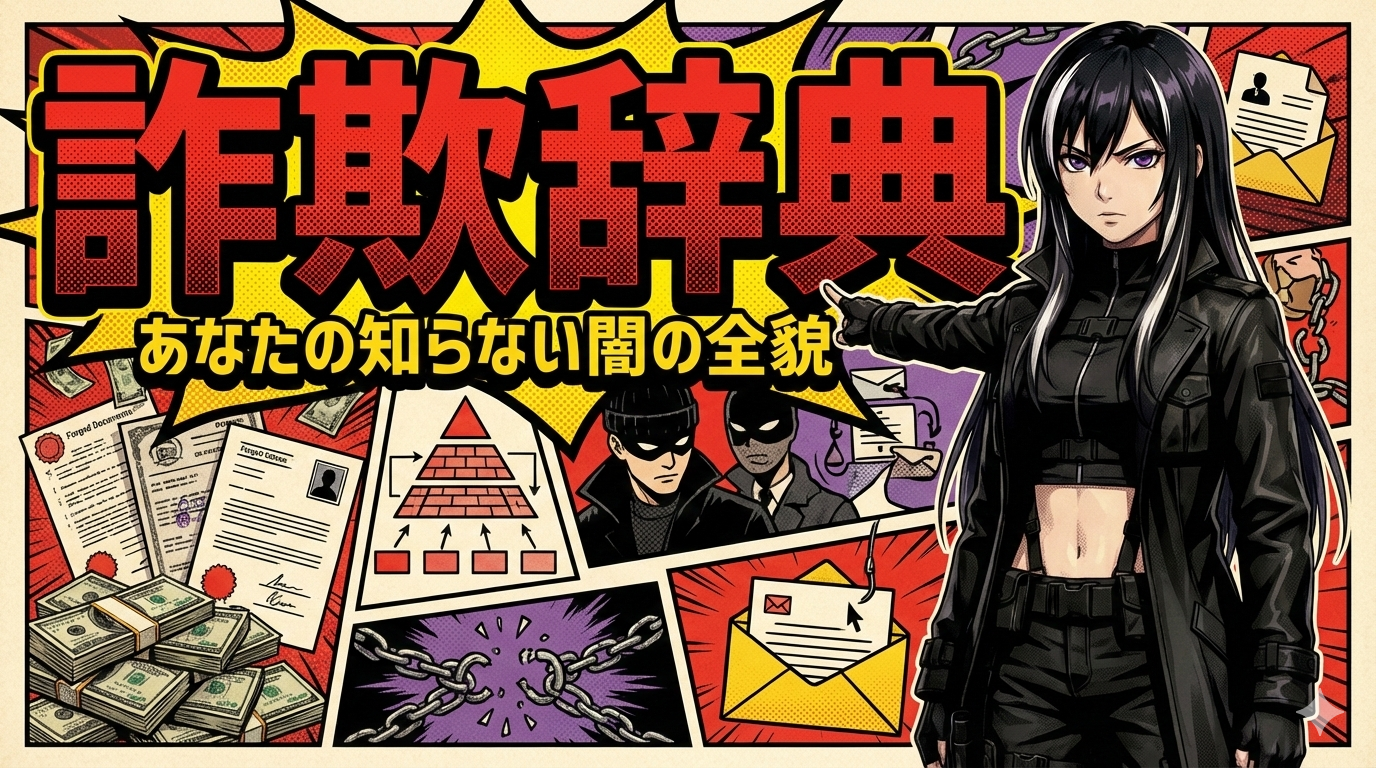


コメント