- 実在する企業やサービスを装い、利用者を欺く詐欺の手口
- メールやSMSなどを通じて偽のWebサイトへ誘導し、個人情報を入力させる
- 盗み取ったID、パスワード、クレジットカード情報などを不正に利用し、金銭的な損害を与える

もっとくわしく知りたい方は続きをどうぞ!
フィッシング詐欺をわかりやすく
フィッシング詐欺とは
フィッシング詐欺は、巧妙な手口で多くの人々を標的にしている。その手口は、あたかも正規の企業やサービスからの連絡であるかのように装い、利用者を油断させることから始まる。電子メールやショートメッセージサービス(SMS)が主な手段として用いられ、受信者を偽のWebサイトへと誘導する。これらの偽サイトは、本物のサイトと酷似しており、注意深く見ないと区別がつかないほど精巧に作られていることが多い。誘導された利用者が偽サイトにID、パスワード、クレジットカード番号などの個人情報を入力してしまうと、その情報は詐欺師の手に渡り、不正な目的で使用される。具体的には、インターネットバンキングへの不正ログイン、クレジットカードの不正利用、個人情報の売買などが挙げられ、被害者は金銭的な損害を被るだけでなく、二次的な被害に遭う可能性もある。
フィッシング詐欺の主な目的は、金銭を得るために利用者の大切な情報を盗み出すことにある。詐欺師は、銀行やクレジットカード会社、大手通販サイトといった信頼性の高い組織になりすまし、利用者に安心感を与えながら罠を仕掛ける。その基本的な概念は、利用者の心理を巧みに利用し、本来であれば警戒するような情報の入力を促す点にある。例えば、「アカウントがロックされた」「不正なアクセスがあった」「未払いの料金がある」といった緊急性を煽るメッセージを送ることで、利用者を焦らせ、冷静な判断力を失わせる。
フィッシング詐欺という言葉は、「魚釣り (fishing)」と「洗練 (sophisticated)」を組み合わせた造語と言われている。これは、巧妙な手口で利用者を「釣り上げる」様子を表している。狙われる情報は多岐にわたり、銀行の口座番号や暗証番号、クレジットカード番号やセキュリティコードはもちろんのこと、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、さらにはSNSやオンラインサービスのID・パスワードなども含まれる。
近年では、手口もさらに巧妙化しており、従来のメールやSMSに加え、QRコードを利用した「クイッシング」と呼ばれる手法や、パソコン画面に偽の警告を表示させてサポート料金を騙し取る「サポート詐欺」なども出現している。これらの新しい手口は、利用者の警戒心をさらに薄れさせ、被害に遭うリスクを高めている。フィッシング詐欺は、常に進化し続ける脅威であり、その手口や目的を理解し、適切な対策を講じることが重要。
フィッシング詐欺の具体的な例
身近な例として、クレジットカード会社から「【重要】お客様のアカウントに不審な利用履歴が確認されました。至急ご確認ください」といったメールが届き、記載されたURLをクリックしてしまい、本物そっくりな偽サイトにログインIDとパスワードを入力してしまうケースがある。また、宅配業者を装ったSMSで「お客様宛にお荷物のお届けがありましたが不在のため持ち帰りました。再配達のご依頼はこちらから」というメッセージとともにURLが送られてきて、安易にクリックしてしまい、個人情報を入力してしまうことも日常的に起こりうる。SNS上では、有名人を装ったアカウントが「フォロワー限定プレゼント企画!応募はこちら」といった投稿を行い、URLをクリックした利用者が個人情報を入力してしまう例も存在する。
具体的な事例としては、大手ECサイトを装ったメールが「お客様のパスワードの有効期限が近づいています。安全のため、パスワードの再設定をお願いします」といった内容で送信され、記載されたURLから偽のログインサイトへ誘導し、アカウント情報を盗み取る手口が報告されている。銀行を装ったケースでは、偽のSMSが「【重要】お客様の口座で不審な取引が確認されました。至急ログインしてご確認ください」といったメッセージとともに送信され、記載されたURLからインターネットバンキングの偽ログイン画面に誘導し、IDやパスワードを詐取する。
また、パソコンの画面に突然「警告!お使いのPCがウイルスに感染しました。今すぐこちらの電話番号に連絡してください」という偽の警告を表示させ、電話をかけてきた利用者にサポート費用と称してクレジットカード情報を聞き出すという手口もある。宅配業者の不在通知を装い、SMSを送信し、偽サイトに誘導して再配達の手続きに必要な情報として、住所や電話番号などの個人情報を入力させる事例も後を絶たない。さらに、携帯電話会社を装い、「未払い料金が発生しております。本日中に下記URLよりお支払いください」といったSMSを送信し、偽サイトに誘導して個人情報を入力させる手口も確認されている。
これらの例からわかるように、フィッシング詐欺は、日常生活で利用する様々なサービスを悪用し、巧妙な手口で利用者を騙そうとする。常に警戒心を持ち、不審な連絡には注意することが重要。
一般的なフィッシング詐欺の流れ
- 1偽装メッセージの送信
詐欺師は、正規の企業や組織を装い、メールやSMSを送信。「不正アクセス」「アカウントロック」「未払い料金」「プレゼント当選」など、利用者の不安や興味を煽る文言が用いられる。
- 2偽サイトへの誘導
メッセージに、偽のWebサイトへのリンクが巧妙に埋め込まれている。短縮URLやスペルミスなど、注意深く確認しないと気付かない工夫が凝らされている。
- 3個人情報・金融情報の詐取
偽サイトは、本物のサイトと酷似したデザインで、利用者を欺く。ID、パスワード、クレジットカード情報、銀行口座情報など、重要な情報の入力を促す。
- 4情報悪用
詐取した情報を使い、アカウントの乗っ取り、不正な買い物や送金などを行う。ダークウェブで個人情報を売買することもある。
- 5手口の巧妙化
短縮URLやスペルミスの悪用、正規サイトのリダイレクト機能悪用など、手口は日々巧妙化している。リアルタイム型フィッシング詐欺では、利用者が偽サイトに入力した情報を、詐欺師が即座に正規サイトで入力するといった手口も報告されている。
- 6二次被害
盗まれた情報を元に更なる詐欺行為が行われたり、個人情報がダークウェブで売買されることにより、予期せぬ二次被害に発展する可能性あり。
フィッシング詐欺の事例
フィッシング詐欺での有名な事件
国内で発生した有名なフィッシング詐欺事件としては、2011年に発生した大規模なオンラインバンキング詐欺事件が挙げられる。この事件では、銀行を装ったフィッシングメールが多数の利用者に送信され、偽のログインページに誘導することで、銀行のIDやパスワードが盗み取られた。攻撃者は、盗んだ情報をもとに被害者の銀行口座に不正アクセスし、預金を第三者の口座へ送金した。被害総額は数億円規模に達し、社会に大きな衝撃を与えた。2017年には、日本航空株式会社(JAL)がビジネスメール詐欺(BEC)の被害に遭い、取引先を装った偽の請求書によって約3.7億円もの損害を被った。警視庁の発表によると、2023年のインターネットバンキングにおける不正送金被害額は87億3130万円と過去最悪を記録しており、この中には企業が被害に遭うケースも含まれている。近年では、特定の企業を標的としたBECの被害が多発しており、巧妙な手口で企業の資金を騙し取る事例が後を絶たない。また、大手金融機関やECサイトの名前を騙ったフィッシング詐欺も頻繁に発生しており、多くの利用者が被害に遭っている。
海外の事例としては、2016年の米国大統領選挙に関連して、政治関係者のメールアカウントが標的となった大規模なフィッシング攻撃が有名。この攻撃では、Googleアカウントのパスワードを入力させるフィッシングメールが使用され、多数の関係者がログイン情報を盗まれた。その結果、数万件に及ぶメールが漏洩し、選挙戦の行方を左右する要因の一つとなったと言われている。2024年には、香港でディープフェイク技術を悪用したビデオ会議詐欺事件が発生し、多国籍企業の会計担当者がCFOを装った詐欺グループに騙され、約38億円もの資金を送金してしまった。この事件のきっかけも、フィッシングメールであったと報告されている。
これらの事件は、フィッシング詐欺が単なるいたずらではなく、深刻な金銭的損失や社会的な影響を引き起こす可能性があることを示している。
フィッシング詐欺についてのよくある質問
- Qフィッシングメールを開いてしまったらどうすればいい?
- A
本文中のURLはクリックせず、個人情報は絶対に入力しない。不審な添付ファイルも開かないようにし、念のためセキュリティソフトでPCやスマートフォンをスキャンすることが推奨される。
- Qもし、偽サイトにIDやパスワードを入力してしまったら?
- A
すぐにパスワードを変更し、他のサービスで同じパスワードを使用している場合も同様に変更する。念のため、サービス提供会社の公式サイトからログインし、不審なログイン履歴がないか確認し、必要であればサービス提供会社に連絡する。
- Qもし、クレジットカード情報を入力してしまったら?
- A
直ちにクレジットカード会社に連絡し、カードの利用停止と再発行の手続きを行う。その後、利用明細を注意深く確認し、身に覚えのない請求がないか確認する。
- Q金銭的な被害に遭ってしまったら?
- A
すぐに利用している金融機関に連絡し、状況を説明する。その後、最寄りの警察署またはサイバー犯罪相談窓口に相談し、被害届を提出する。国民生活センターや消費生活センターへの相談も有効。
- Qフィッシング詐欺かどうか判断に迷ったら?
- A
メールやSMSに記載された連絡先を信用せず、必ず公式サイトなどで正しい連絡先を調べて問い合わせる。フィッシング対策協議会などの情報も参考になる。
- Qスマホで簡単にできるフィッシング詐欺対策は?
- A
セキュリティソフトをインストールし、OSやアプリを常に最新の状態に保つ。携帯電話会社が提供する迷惑SMSフィルタリング機能などを活用する。また、ログインが必要なサイトへは、メールやSMSのリンクからではなく、公式サイトや公式アプリからアクセスする習慣をつけることが重要。
フィッシング詐欺が生まれた歴史や背景
「phishing」という言葉が初めて使われたのは1990年代と言われている。その語源は、「fishing(釣り)」という単語をハッカーのスラングとして変化させたもので、「phreaking(電話回線の不正利用)」という言葉の影響を受け、”f”が”ph”に変わったと考えられている。
初期のフィッシング詐欺が広く認識されるようになったのは2003年頃、アメリカ国内で被害が急増したことがきっかけであった。日本国内では、2004年12月に最初の被害が確認されたと警察庁が発表している。当初の手口は比較的単純なものが多かったが、インターネットとメールサービスの普及とともに、その手口は徐々に巧妙化し、多様化していった。スマートフォンの普及に伴い、SMSを利用したフィッシング詐欺、いわゆる「スミッシング」も登場し、新たな脅威となっている。
近年、フィッシング詐欺の被害は再び増加傾向にあり、2023年には被害額が過去最悪を記録した。この背景には、コロナ禍におけるインターネット利用の増加や、ECサイトの利用拡大が影響していると考えられる。また、国境を越えて海外の犯罪組織が日本の消費者をターゲットにするケースも増えており、国際的な連携による対策が求められている。
フィッシング詐欺の被害にあってしまいやすい人物や状況
フィッシング詐欺の被害に遭いやすいのは、インターネットやオンラインサービスをあまり利用しない初心者や、セキュリティ意識が低い人。また、心理的に慌てやすい状況にある人や、不安を感じやすい人も狙われやすい。複数のサイトで同じIDやパスワードを使い回している人も、一つの情報が漏洩しただけで芋づる式に被害が拡大する可能性があるため注意が必要。
被害に遭いやすい状況としては、身に覚えのないメールやSMSを受け取った時、「重要」「緊急」「不正利用」といった言葉で焦らせる内容のメッセージを受け取った時、電子メールやSMSに記載されたURLを安易にクリックする時、そして個人情報やクレジットカード情報の入力を促された時などが挙げられる。
これらの被害を防ぐためには、以下の点に注意する必要がある。まず、不審なメールやSMSに記載されたURLは絶対にクリックしないこと。サービスへのログインが必要な場合は、メールやSMSのリンクからではなく、事前にブックマークした公式サイトや公式アプリからアクセスする習慣をつける。URLのドメイン名が正しいかどうかを必ず確認し、少しでも不審な点があればアクセスしない。IDやパスワードは、複数のサイトで使い回すのをやめ、それぞれ異なる強力なパスワードを設定する。可能な限り、ワンタイムパスワードや二段階認証などのセキュリティ機能を設定し、不正アクセスを防ぐ。セキュリティソフトを導入し、常に最新の状態に保つことも重要。携帯電話会社などが提供するセキュリティ設定も積極的に活用するとよい。そして、クレジットカードの利用明細を定期的に確認し、身に覚えのない請求がないかをチェックすることも被害の早期発見につながる。
フィッシング詐欺のまとめ
- フィッシング詐欺は、信頼できる組織を装い、メールやSMSなどで偽サイトへ誘導して個人情報を盗み取る手口である
- 主な目的は金銭的な利益を得ることで、盗まれた情報は不正送金やクレジットカードの不正利用などに悪用される
- 被害に遭わないためには、不審なメールやSMSのリンクはクリックせず、公式サイトや公式アプリからアクセスするなどのセキュリティ対策を講じることが不可欠である

以上、フィッシング詐欺についてでした!これで、フィッシング詐欺はあなたの知識となりましたか?
被害にあわないように対策しましょう。まだまだ足りないという方は、コメントをぜひください。お待ちしております。

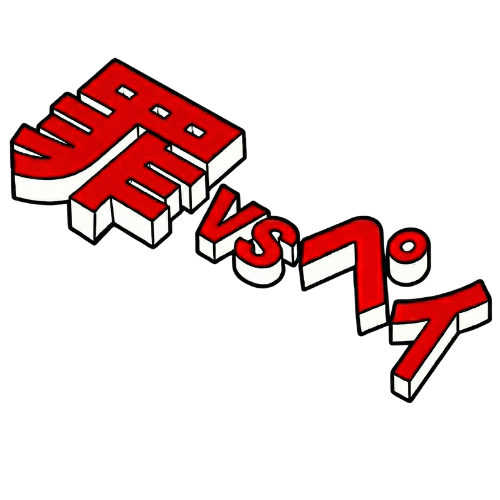


コメント