- 利用した覚えのないサービス料金などを請求する詐欺
- ハガキ、メール、偽の警告画面など様々な方法で接触
- 不安を煽り、電子マネー購入指示などで金銭をだまし取る

もっとくわしく知りたい方は続きをどうぞ!
架空請求詐欺をわかりやすく
架空請求詐欺とは
架空請求詐欺とは、実際には利用していないサービスや購入していない商品について、あたかも利用・購入したかのように装い、不当にお金を支払わせようとする詐欺行為。その主な目的は、被害者を心理的に追い込み、冷静な判断力を奪って金銭をだまし取ることにある。
この詐欺の基本的な概念は「存在しない債務の請求」。詐欺師は、有料サイトの未払い料金、情報料、サービスの解約料など、もっともらしい名目を使い、請求書や通知を送りつける。これらの請求は全く根拠がなく、支払う義務は一切ない。しかし、突然の請求や、「法的措置」「差し押さえ」といった脅迫的な文言によって、被害者は不安や恐怖を感じ、言われるがままに支払ってしまうことがある。
手口は電話、SMS、電子メール、ハガキ、ウェブサイト上のポップアップ警告など多岐にわたる。特に、実在する企業名(例:NTTファイナンス)や公的機関(例:法務省、裁判所)をかたることで、請求の正当性を信じ込ませようとするケースが多い。支払い方法も、銀行振込だけでなく、コンビニでの電子マネー(プリペイドカード)購入や、特定の支払い番号を使ったレジ払いなど、足がつきにくい方法を指定する傾向がある。
重要なのは、これらの請求が「架空」であるという点。身に覚えがなければ、慌てず、無視することが基本的な対応となる。
架空請求詐欺の具体的な例
架空請求詐欺は、私たちの日常生活の中に様々な形で現れる。以下に具体的な事例をいくつか紹介する。
SMSによる請求
ある日、スマートフォンに「有料動画サイトの未納料金が発生しております。本日中にご連絡なき場合、法的手続きに移行いたします。○○相談窓口03-XXXX-XXXX」というSMSが届く。全く心当たりがないが、「法的手続き」という言葉に不安を感じ、記載された番号に電話してしまう。電話口の相手は「サイト利用料29万5千円が未納です。今日中に支払えば、後日95%返金されます」などと言葉巧みに支払いを促す。焦りから、指示されるままコンビニで電子マネーを購入し、カード番号を伝えてしまう。しかし、返金されることはなく、お金をだまし取られる。
ハガキによる請求
自宅に「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」など、もっともらしい差出人名で「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届く。内容は「契約不履行による民事訴訟が提起された。連絡がない場合は給与、動産、不動産の差し押さえを強制的に執行する」といった脅迫的なもの。不安になり、ハガキに書かれた電話番号に連絡すると、弁護士を名乗る人物を紹介され、訴訟取り下げ費用や示談金として高額な金銭を請求される。指示通りに現金をレターパックで送付したり、プリペイドカードを購入して番号を伝えたりしてしまう。
パソコン画面上の偽警告(サポート詐欺)
パソコンでインターネットを閲覧中、突然「ウイルスに感染しました」「システムが破損しています」といった警告画面が表示され、同時に警告音や音声が流れる。画面には「マイクロソフトサポートセンター」などの名称と電話番号が表示され、電話をかけるように指示される。電話すると、片言の日本語を話すオペレーターが「遠隔操作で修復します」「セキュリティソフトの購入が必要です」などと言い、サポート費用として数万円から数十万円を請求する。支払い方法として、コンビニで電子マネーカードを購入し、番号を伝えるよう指示される。実際にはウイルス感染しておらず、不要な支払いをしてしまう。
これらの事例からわかるように、詐欺師は実在の企業や公的機関を装い、法的な手続きや差し迫った危険をちらつかせることで、被害者の不安を最大限に煽り、冷静な判断をさせずに金銭をだまし取ろうとする。連絡手段や支払い方法が多様化している点も特徴。
架空請求詐欺が発生する手順
- 1接触(通知)
詐欺師は、SMS、電子メール、ハガキ、あるいはウェブサイト上のポップアップ広告などを用いて、ターゲットに最初の接触を試みる。通知内容は、「未払い料金がある」「訴訟を起こされた」「ウイルスに感染した」など、受け取った側が不安や焦りを感じるようなものであることが多 。この段階では、不特定多数に無差別に送られている場合が多い。
- 2連絡誘導
通知には必ず連絡先(電話番号やメールアドレス、URLなど)が記載されており、「確認のため」「訴訟取り下げのため」「サポートのため」といった名目で、ターゲットからの連絡を促す。公的機関や実在の企業名をかたり、信頼性を装う。
- 3不安の増幅・脅迫
ターゲットが連絡してくると、詐欺師はより具体的な脅し文句を用いる。「今日中に支払わないと裁判になる」「延滞金が加算される」「個人情報を調査する」「勤務先に連絡する」などと畳みかけ、精神的に追い詰める。時には、「支払えば後で返金される」といった嘘の安心材料を提供することもある。
- 4個人情報の聞き出し(任意)
会話の中で、氏名、住所、生年月日、勤務先などの個人情報を巧みに聞き出そうとすることがある。これにより、後の請求や別の詐欺に利用しようとする。
- 5支払い要求
具体的な金額を提示し、支払いを強く要求する。当初の請求額に、延滞料、調査費用、弁護士費用などの名目で金額が上乗せされることもある。
- 6支払い方法の指示
支払い方法として、銀行振込ではなく、コンビニでの電子マネー(プリペイドカード)購入と番号通知、ギフトカード購入、収納代行サービス、ATM操作による振込(還付金詐欺と複合する場合)、現金送付(レターパックなど)を指示する。これらは追跡されにくい支払い方法。
- 7支払いの実行
指示に従い、ターゲットが支払いを行ってしまう。コンビニ店員に怪しまれないよう、「自分で使うゲーム用だ」などと嘘の説明をするよう指示されることもある。
- 8追加請求(繰り返しの被害)
一度支払ってしまうと、「他にも未払いがある」「和解手続きに費用が必要」などと、別の名目でさらなる支払いを要求されることがある。被害者が「支払ってくれる人」と認識され、被害が拡大するケースも少なくない。
この一連の流れにおいて、詐欺師はターゲットに考える時間を与えず、不安や焦りを煽り続けることで、冷静な判断を妨げることを狙っている。
架空請求詐欺に関する事例
架空請求詐欺は、個人を対象とした小規模なものから、社会的に注目を集める大規模な事件まで、数多く発生している。以下に、報道された事例や特徴的な事件をいくつか紹介する。
法務省かたりハガキ送付事件(2017年頃~)
「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」や「民事訴訟管理センター」といった、実在しない公的機関名をかたるハガキが全国的に大量送付された事件。ハガキには「訴訟が提起された」「財産を差し押さえる」などと記載され、連絡を促す内容であった。連絡してきた被害者に対し、弁護士紹介料などの名目で金銭をだまし取る手口で、国民生活センターや法務省が繰り返し注意喚起を行った。この手口により数百万円を詐取された被害者も報告されている。
NTTファイナンスかたり自動音声・SMS詐欺(継続的に発生)
実在する企業「NTTファイナンス」を名乗り、「未納料金がある」という自動音声電話やSMSを送りつける手口が多発している。国際電話番号からの着信や、「オペレーターに繋ぐ場合は1番を押してください」といったガイダンスが特徴。連絡してきた被害者に対し、「支払わないと裁判になる」などと脅し、コンビニでの電子マネー購入を指示する。NTTファイナンス自身もウェブサイト等で注意喚起を行っており、同社がSMSや国際電話で料金請求を行うことはないと明言している。訪問による集金詐欺も報告されている。
高額被害事件(例:横浜市3億2000万円被害2024年発覚)
架空請求詐欺による被害額が極めて高額になるケースも存在する。2025年2月に報道された事例では、横浜市の50代男性が、通信会社職員を名乗る男らからの「電話回線の未納料金がある」という電話を信じ込み、約半年間に76回にわたり、合計約3億2000万円を振り込むなどしてだまし取られた。これは神奈川県内の特殊詐欺被害額としては過去最高額と報じられた。一度信じ込ませると、様々な名目で繰り返し金銭を要求し、被害が雪だるま式に膨らむ危険性を示している。
サポート詐欺による高額被害(例:徳島県100万円被害2024年報告)
パソコンの偽警告画面(サポート詐欺)から高額被害につながるケースもある。徳島県で報告された事例では、70代男性がパソコン画面の警告表示に従い連絡したところ、遠隔操作でインターネットバンキングにアクセスされ、データ復旧代金名目で5万円を振り込むよう指示された。男性は5万円と入力したが、実際には100万円が振り込まれており、遠隔操作中に金額を改ざんされた可能性が指摘されている。
これらの事件は、手口の巧妙さ、被害の深刻さ、そして誰にでも起こりうる危険性を示している。公的機関や有名企業をかたる手口は後を絶たず、常に警戒が必要。
架空請求詐欺についてのよくある質問
- Q身に覚えのない請求が来たら、どうすればいいか?
- A
絶対に無視することが基本。支払う必要は全くない。メール、SMS、ハガキなどに記載されている電話番号やリンクには、絶対に連絡・アクセスしない。連絡してしまうと、相手に個人情報を知られたり、さらに脅されたりする危険がある。不安な場合は、請求元に連絡するのではなく、消費生活センター(電話番号188)や警察相談専用電話(#9110)に相談するべき。
- Q間違って連絡してしまった場合はどうすればいいか?
- A
それ以上の個人情報(氏名、住所、生年月日、家族構成、銀行口座情報など)は絶対に伝えない。相手が脅してきても、冷静に対応し、電話を切る。しつこく請求が続くようであれば、弁護士や消費生活センターに相談することを推奨する。可能であれば、電話番号やメールアドレスの変更も検討すべき。
- Q「裁判」「差し押さえ」と書かれているが、本当か?
- A
ほとんどの場合、単なる脅し文句。本物の裁判所からの法的な通知(支払督促や訴状など)は、「特別送達」という特別な書留郵便で送達されるのが原則であり、普通郵便のハガキや封書、電子メールで届くことは基本的にない。もし「特別送達」で裁判所からの書類が届いた場合は、無視せずに、記載されている裁判所の公式な電話番号(書類記載の番号ではなく、自分で調べた番号)に連絡して真偽を確認するか、消費生活センターや弁護士に相談する必要がある。
- Q請求内容に少し心当たりがある気がするが、どうすればいいか?
- A
それでも安易に支払うべきではない。詐欺師は、過去に無料サンプルを請求した、無料サイトに登録したなどの、被害者のわずかな記憶や心当たりにつけ込んでくることがある。契約内容や請求根拠が不明確な場合は、詐欺の可能性が高い。自分で判断せず、まずは消費生活センターなどに相談することが重要。
- Qなぜ詐欺師が自分の名前や住所を知っていることがあるのか?
- A
過去に利用したサービスからの情報流出や、名簿業者などから不正に入手した個人情報リスト(名前、住所、電話番号など)を使用している可能性がある。名前や住所を知られていても、請求自体が架空であれば支払う義務はない。むしろ、相手に連絡することで、さらに詳しい個人情報を知られてしまうリスクがあるため、連絡は避けるべき。
- Q電子マネーでの支払いを要求されたら、どうすればいいか?
- A
ほぼ100%詐欺であると判断してよい。「コンビニで電子マネー(プリペイドカードやギフトカード)を買って、裏面の番号を教えて」という指示は、架空請求詐欺の典型的な手口。公的機関や正規の事業者が、未払い料金などの支払いをこの方法で要求することは絶対にない。絶対に指示に従わず、支払いを拒否し、警察や消費生活センターに相談すべき。
架空請求詐欺が生まれた歴史や背景
架空請求詐欺は、不特定多数の者を対象とし、電話やメールなど非対面の手法で金銭をだまし取る「特殊詐欺」の一類型として位置づけられる。その歴史は、特殊詐欺全体の変遷と密接に関連している。
特殊詐欺は、2000年代初頭に「オレオレ詐欺」として社会問題化した。当初は息子や孫を装って電話をかけ、事故の示談金などを名目に現金を振り込ませる手口が主流。しかし、手口が多様化し、単に家族を装うだけでなく、利用した覚えのない料金を請求する「架空請求」タイプの手口も早くから認識されていた。
この手口の多様化を受け、警察庁は2004年に、これらの詐欺を総称して「振り込め詐欺」と命名した。その後、犯人が被害者宅を訪問して現金やキャッシュカードを受け取る手口(手交型)や、カードをすり替えて盗む手口(詐欺盗)が増加したことなどから、実態に合わせて「特殊詐欺」という名称・分類が用いられるようになった。警察庁は令和2年(2020年)にも手口の分類を見直しており、架空料金請求詐欺はその主要な類型の一つとして扱われている。
架空請求詐欺の手口自体も、時代とともに変化してきた。初期には、電子メールやハガキで単純に未払い料金を請求するものが多かったと考えられる。その後、スマートフォンの普及に伴い、SMSを利用した「スミッシング」と呼ばれる手口が登場した。また、インターネット利用中に偽の警告画面を表示させる「サポート詐欺」も増加している。
支払い方法も、銀行口座への振込から、追跡が困難なコンビニでの電子マネー購入指示へと変化が見られる。これは、口座凍結などの対策が進んだことへの対応と考えられる。
統計データを見ると、特殊詐欺全体の被害額は増減を繰り返しながらも高水準で推移しており、架空請求詐欺もその一翼を担っている。例えば、平成16年(2004年)頃に被害がピークに達した後、増減を経て、近年再び被害額が増加傾向にあるとの報告もある。国民生活センターへの架空請求に関する相談件数も、2017年度には年間約20万件に達するなど、依然として多くの人々が被害に遭ったり、不安を感じたりしている状況がうかがえる。
架空請求詐欺が後を絶たない背景には、不正に入手された個人情報(名簿)の流通、匿名性の高い通信手段や決済手段の存在、そして後述するような人間の心理的な隙を突く巧妙な手口の存在があると考えられる。
架空請求詐欺の被害にあってしまいやすい人物や状況
架空請求詐欺の被害は誰にでも起こりうるが、特定の状況や心理状態にある人が狙われやすい、あるいは騙されやすい傾向が見られる。ただし、特定の属性だけが危険というわけではなく、状況と心理が複合的に作用することを理解する必要がある。
- 情報へのアクセスや理解の差:インターネットや新しいサービス、法的な手続きに関する知識が乏しい場合、詐欺師の説明や脅し文句を真に受けてしまいやすい。特に、公的機関や大手企業名をかたられると、その権威性から疑いにくくなる。
- 権威への弱さ:警察、裁判所、弁護士、大手企業といった権威ある名称を出されると、その指示に従いやすい傾向がある。
- 切迫感・恐怖への反応:「今日中に支払わないと大変なことになる」「裁判になる」「差し押さえる」といった言葉で時間的な猶予を奪われ、恐怖や焦りから冷静な判断ができなくなる。詐欺師はこの心理状態(思考停止)を意図的に作り出す。
- 社会的評価への懸念:「家族や会社に知られたくない」「恥ずかしい」といった世間体を気にする心理につけ込まれ、問題を内密に解決しようとして支払ってしまうことがある。この心理は、被害に遭った後の相談や通報をためらわせる要因にもなる。
- 過信・正常性バイアス:「自分は絶対に騙されない」「こんなことは自分には起こらないはずだ」という思い込み(正常性バイアス)が、かえって警戒心を低下させ、不審な点を見過ごす原因となりうる。特殊詐欺被害者の多くが、事前に報道などで手口を知っていたにも関わらず、「自分は大丈夫」と思っていたというデータもある。また、「騙されたふりをして撃退しよう」と考えることも、相手との接触を招き、リスクを高める可能性がある。
- 認知的不協和の解消:「おかしい」と感じつつも、相手の指示に従ってしまった場合、その矛盾を解消するために「これは本物の請求だ」「支払うのが正しい」と自分の考えの方を修正してしまう心理が働くことがある。孤立・相談相手の不在:日頃から家族や地域との交流が少なく、孤立している場合、突然の請求に不安を感じても誰にも相談できず、一人で抱え込んで詐欺師の要求に応じてしまうリスクが高まる。特に高齢者の一人暮らしなどは、詐欺師にとって狙いやすい状況とされることがある。
- 偶発的な要因:過去に何らかのサイトに登録したかもしれないという曖昧な記憶、あるいは単に運悪く個人情報が流出してリストに載ってしまった、仕事で疲れている時や他の心配事がある時に注意力が散漫になっているなど、本人の特性とは別に、状況によって被害に遭いやすくなることもある。
重要なのは、詐欺師がこれらの心理的な隙や状況を熟知し、意図的に悪用しているという点。したがって、「自分は大丈夫」と過信せず、誰もが被害に遭う可能性があるという認識を持ち、日頃から対策を意識することが重要となる。
架空請求詐欺:危険なサインと正しい対応
| 危険なサイン | 具体例 | やってはいけないこと | 正しい対応 |
|---|---|---|---|
| 身に覚えのない請求 | 「未納料金あり」のSMS、ハガキ、メール、電話 | 連絡する リンクをクリックする 支払う | 無視する 必要なら公式窓口で確認 |
| 脅迫的な文言 | 「法的措置」「裁判」「差し押さえ」「本日中」 | 慌てて従う 要求に応じる | 無視する 不安なら相談 |
| 異常な支払い方法の要求 | 「コンビニで電子マネー、ギフトカードを買って番号を教えろ」 | 購入する 番号を教える 現金送付 | 支払いを拒否 詐欺と判断し、相談 |
| 偽の警告画面 (サポート詐欺) | 「ウイルス感染」のポップアップと警告音、電話番号表示 | 表示された番号に電話する 遠隔操作を許可する | 無視する ブラウザ強制終了またはPC再起動 不安なら専門家や警察に相談 |
| 公的機関 有名企業かたり | 「法務省」「NTTファイナンス」などを名乗るが連絡先が非公式 | 記載された連絡先に連絡する | 無視する 公式ウェブサイトや正規の連絡先で真偽を確認 |
| 個人情報の要求 | 電話やメールで口座番号、暗証番号、カード情報などを聞かれる | 教える | 絶対に教えない 電話を切る メールを削除する |
| 「後で返金される」等の甘い言葉 | 「支払えば95%返金」、「保険適用」 | 信じて支払う | 無視する 詐欺師の嘘である可能性が高い |
架空請求詐欺のまとめ
- 架空請求詐欺は「根拠のない請求」による詐欺
- 怪しい請求には「絶対に連絡しない・支払わない」
- 不安や迷いを感じたら、すぐに「相談する」

以上、架空請求詐欺についてでした!これで、架空請求詐欺はあなたの知識となりましたか?
被害にあわないように対策しましょう。まだまだ足りないという方は、コメントをぜひください。お待ちしております。

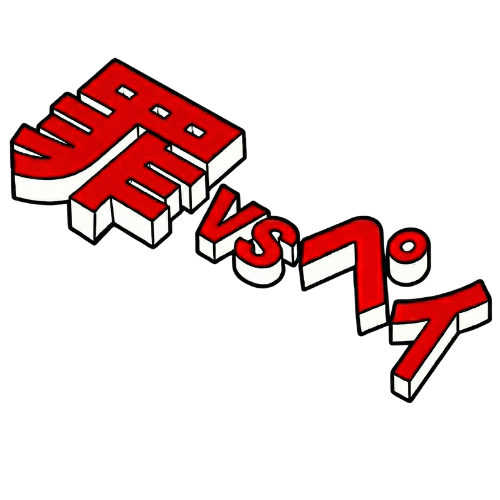


コメント